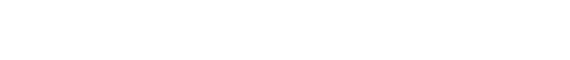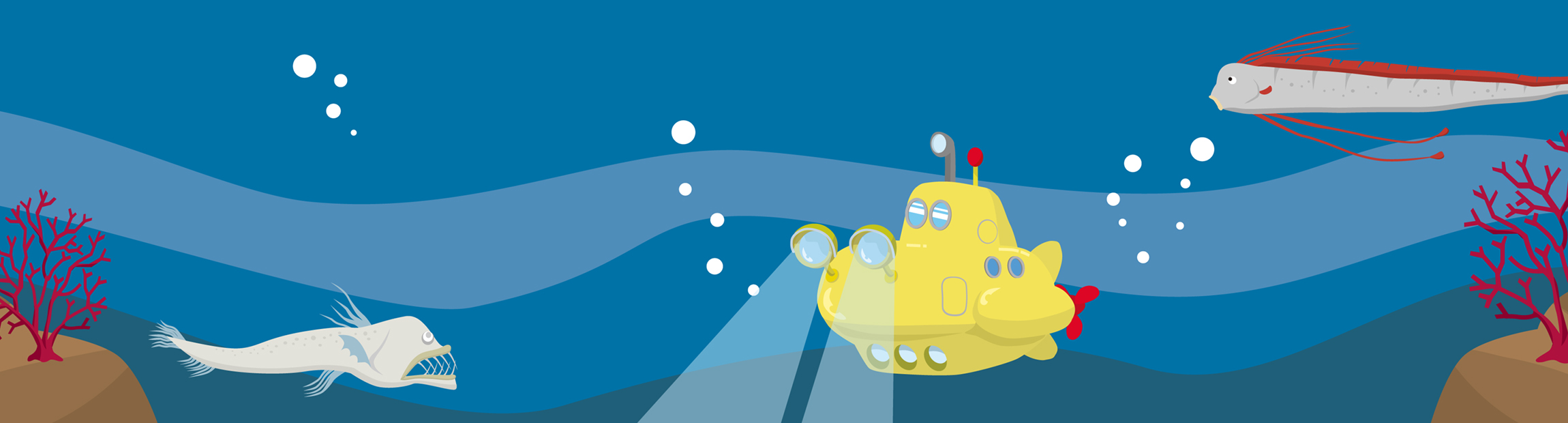
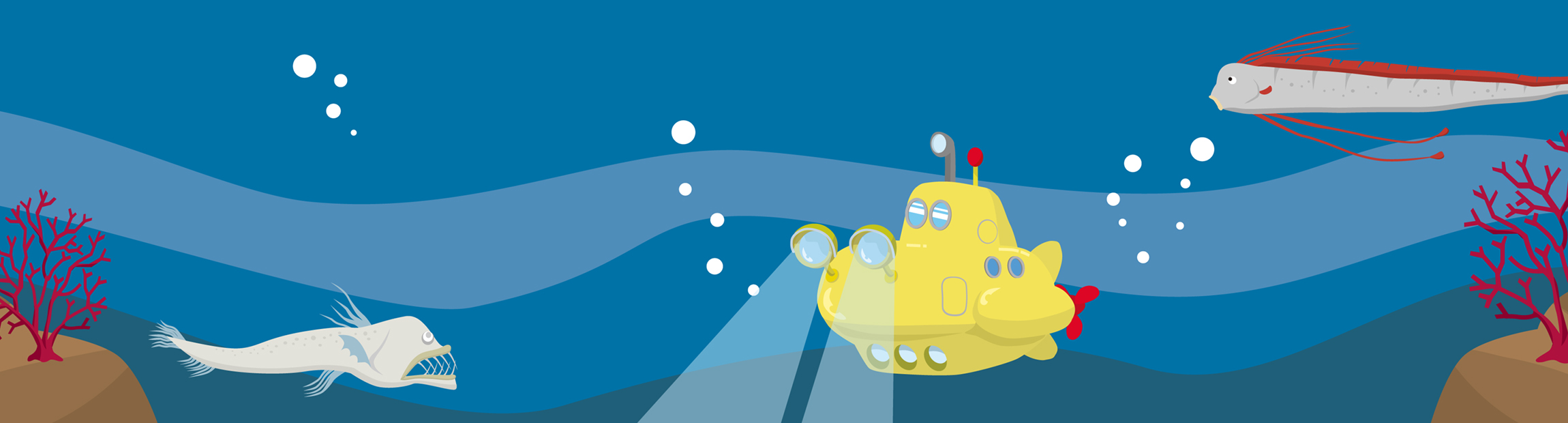



和歌山県南部では成魚が水深200mで延縄により、体長12cmの若魚は田辺湾水深30mで底曳網によりとれます。練製品に使われます[2]。
ウエブやYouTubeなどでさまざまな調理方法が紹介されています。味については好みが分かれるようです。
背鰭は1基で、擬鎖骨棘(ぎさこつきょく)が不明瞭なことで、ミシマオコゼと見分けられます[4]。写真の左側がミシマオコゼ、右側がアオミシマです。
英名はBluespotted(青い斑点のある) stargazer(ミシマオコゼ)と言います。
ミシマオコゼ科の魚については、ミシマオコゼのページをご覧ください。
レア度 ★(★の数が多いほどレアです)
1. 中坊徹次(編). 2020. 小学館の図鑑Z 日本魚類館. 小学館
2. 池田博美・中坊徹次. 2015. 南日本太平洋沿岸の魚類. 東海大学出版部
3. 益田一ほか(編). 1988. 日本産魚類大図鑑, 第二版. 東海大学出版会
4. 中坊徹次(編). 2013. 日本産魚類検索 全種の同定, 第三版. 1–3巻. 東海大学出版会
5. 渋澤敬三. 1959. 日本魚名の研究. 角川書店
6. 山田梅芳ほか. 2007. 東シナ海・黄海の魚類誌. 東海大学出版会