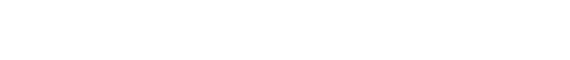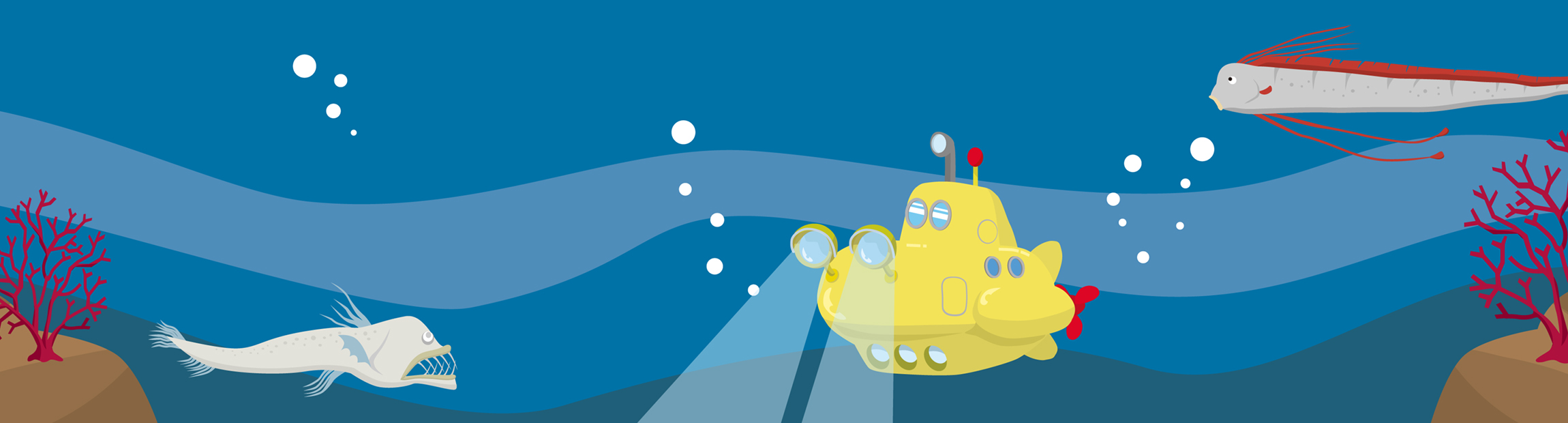
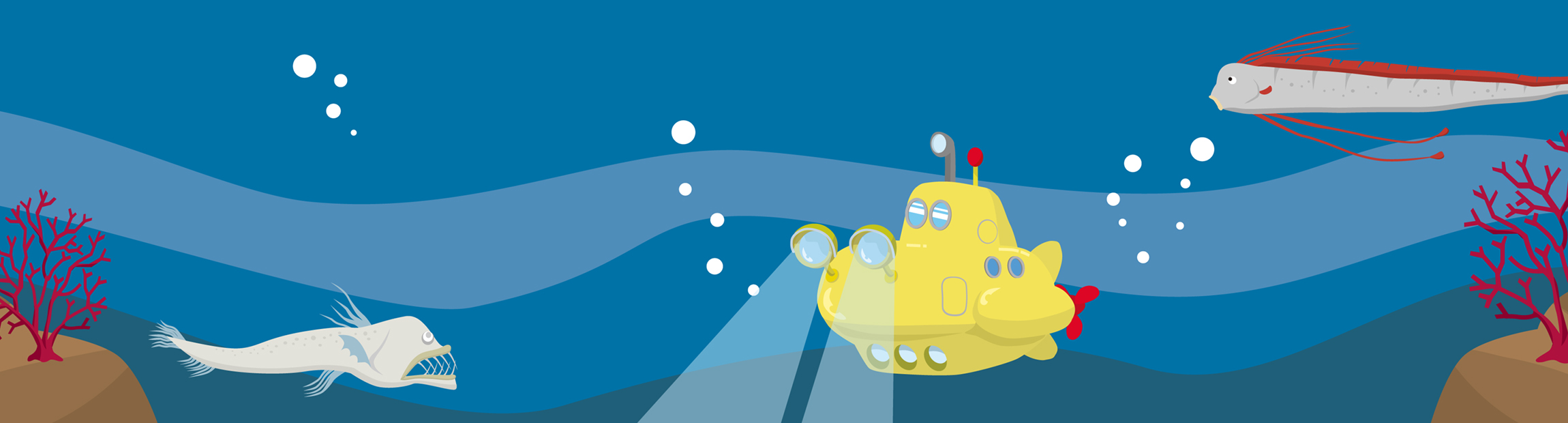







シギウナギは、”ウナギ”と名前がついていますが、ウナギ科の魚ではなく、ウナギ目シギウナギ科の魚で、鴫(シギ)という鳥の嘴(くちばし)のように、顎が細長く上下に伸びていている姿から鴫鰻(シギウナギ)と呼ばれているようです。
未成熟魚と雌では、吻(ふん)がくちばし状に長く突出し、上顎は上方へ、下顎は下方へ湾曲し、両顎はかみ合いません。[1]
雄は性成熟期に変態し、顎の短縮,歯の脱落などの現象が生じます。[1] [6]
このような形態学的変化のために、過去には別々の属、さらには別の亜目に分類されたこともあるようです。[6]
シギウナギ科は世界で3属9種(Avocettina属(4種)、Labichthys属(2種)、Nemichthys属(3種))が知られ、うち日本に分布するのは2属3種(Nemichthys属(1種)シギウナギ、Avocettina属(2種)クロシギウナギとクロシギウナギモドキ)です。[3][6]
シギウナギは尾部の後端が糸状で側線孔が3列ですが、クロシギウナギ・クロシギウナギモドキは尾部の後端が糸状でなく、側線孔が1列である等で区別できます。かみ合わない口を開けた状態で垂直に体を保ち、細い顎に絡まった甲殻類等を食べているようです。[3]
本稿でご紹介する画像には、白い個体と黒い個体があります。白い個体については、尾部が糸状であるため、シギウナギと思われます。一方、黒い個体についても臀鰭が体の前方まで達しているのでシギウナギであると推察されます。またこの黒い個体は顎が長く伸びているため、オスだと思われます。[2]
遊泳性の深海魚で海底から離れて浮遊遊泳生活を送っていて、底曵網漁で捕獲されることがあります。食用とはされていませんが、インターネット上では刺身や天ぷらにして食べてみたとの記事もあります。
レア度 ★☆☆☆☆(★の数が多いほどレアです)
1. 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
2. 中坊徹次(編). 2013. 日本産魚類検索 全種の同定, 第三版. 1–3巻. 東海大学出版会
3. 中坊徹次(編). 2020. 小学館の図鑑Z 日本魚類館. 小学館
4. 池田博美・中坊徹次. 2015. 南日本太平洋沿岸の魚類.東海大学出版部
5. 益田一ほか(編). 1988. 日本産魚類大図鑑, 第二版. 東海大学出版会
6. J. S. Nelson, T. C. Grande, and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the World Fifth Edition, P151, John Wiley and Sons.